ecoだけ ブース
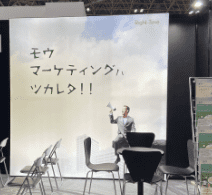
こんにちは。
「エコロジーとエコノミーをビジネス化する」を目標に活動している”ecoだけマーケター“たちが、最近気になる環境やDXにまつわる話題を短く紹介するエコなブログです。「○○したいけど、○○できない」とお悩みの、何かとお疲れ様の皆様に向けて、小さな取り組みなどを紹介します。コーヒーブレイクや休憩の合間にお読みください。

ひらけ、未来への扉(まとめ記事)
AI技術が化粧品開発に深く浸透しつつあります。既に複数の企業が研究段階からAIを導入し、処方探索・評価・製造・消費者体験に至るまでのプロセスを変革しつつあります。
具体的には、処方探索の高速化からパーソナライズソリューション、サステナビリティ設計まで、研究開発(R&D)のさまざまなプロセスでAI活用が進み始め、開発者と消費者に多彩な恩恵をもたらしています。処方の候補を素早く絞り込む、評価を客観的に支える、製造のムダを減らす、体験価値を高める——こうした流れが研究段階から店頭・オンラインまで一本の線になりつつあります。かつては研究者の経験と直感に大きく依存していた領域に、データとアルゴリズムが組み込まれることで、効率と創造性が同時に拡張されているのです。
ただ、その裏には、「データの偏り」「過度な期待」「プライバシー懸念」などの影も存在します。本稿では両面から具体的に探りつつ、未来に少しずつ幸せを積み重ねるための処方箋を、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。
国内の多くの研究現場では、ベテランの暗黙知と実験データを組み合わせて、処方探索の遠回りを減らすアプローチが広がっています。 感覚に頼りがちな評価(たとえば肌の印象変化)も、画像・計測・言語データを用いて見える化するなど、評価の再現性が上がれば、試作の回数やリードタイムは自然とスリムになります。 さらに、分野横断の知見を社内で共有しやすくする“ナレッジ基盤”づくりも進み、「人に依存しすぎないR&D」へのシフトが各所で見られます。
ピックアップ事例 ポーラ化成「AIMPOLAR」
AIMPOLARは、研究者の“経験知”と膨大な実験データを融合し、処方探索を最短距離で導くAIシステムです。化粧品の処方は、成分の種類や配合比率、相互作用などの組み合わせが膨大で、試作・失敗を繰り返しながら最適解に近づくのが従来の姿でした。
AIは、過去の実験結果と現在の研究者の直感を同時に扱うことで「成功確率の高い配合候補」を優先的に提示します。結果、時間とコストを削減するだけでなく、再現性の高い研究体制を作り出しています。※
他にも、各社がいろいろな取り組みを進めていますが、全てを紹介するのは膨大な情報量になるため、またの機会にご紹介します。
海外では、生成AIを研究・評価・企画に横断的に使う基盤化が進行中です。
試験計画のシミュレーションや、結果の自動解析、消費者の声のリアルタイム集約など、研究室と市場の距離を縮める工夫が目立ちます。
香料や素材の分野では、ロボティクスとAIを組み合わせた自動試作ラインの導入も一般化。単純作業を機械に任せ、研究者は仮説づくりと検証ストーリーの設計に集中するスタイルが定着しつつあります。
事例 P&G
P&Gは、OlayなどのブランドでAIを使った肌診断スキンケア・アドバイザー・サービスを展開。研究者は消費者から得られる膨大な肌データを即時に分析し、商品開発に反映できることで、研究と消費者体験を直結させています。※
香りの設計は「芸術」と呼ばれる領域ですが、ここにもAIが補助的に導入されています。
AIが新しい香料の処方を提案し、持続可能性や消費者嗜好を考慮したり、AIが候補を作成し、調香師はそこから発想を広げることに役立ったり、中小ブランド向けにAIプラットフォームを開放し、誰でも香り開発に参加可能になったりと、使い勝手が広がります。
ここで重要なのは「AIが香りを作る」のではなく、AIが“調香師のパートナー”になること。職人技を補い、発見を加速する役割です。
化粧品開発では安全性評価が欠かせません。
機械学習を用いた刺激性予測モデルなど、動物実験の代替として注目されています。EUでも新AI規制(AI Act)が施行され、AIを使う場合には「データの質」「人間の監督」「結果の透明性」が必須となります。
安全性評価や表示・広告の妥当性は、これまで以上に説明責任が求められます。 AIは、既存のデータからリスクの予兆を早めに示し、評価プロセスの記録を整えるのに向いています。「AIに任せたので正しいだろう」ではなく、人の監督と検証が前提です。最初から「説明するつもりで設計する」姿勢が、結果としてスムーズな規制対応につながります。
つまりAIは効率化ツールであると同時に、規制遵守と説明責任を果たすためのパートナーにもなっているのです。
近年注目されるマイクロバイオーム研究では、AIが大量の菌叢データを解析し、肌状態と成分の相関を明らかにしています。肌状態と原料効果の関係を可視化したり、肌菌叢に基づく新しい「肌タイプ」分類を提案したり。従来の「乾燥肌・脂性肌」といった分類を超え、菌叢ベースでの新しいスキンケア設計が可能になります。
1-1. 開発スピードと効率の飛躍的向上…絞り込みが早く、試作回数が減らせる
1-2. コスト削減および廃棄軽減…原料・工数・エネルギーのロスが小さくなる
1-3. パーソナライズ設計への応用…個人の経験がデータとして共有され、属人化も緩む
1-4. 新たな創造性の源泉としてのAI…AIが候補を洗い出し、人は「良い理由づくり」に集中できる
1-5. 品質管理の高度化とスマート製造への展開…評価のばらつきを抑え、再現性のある判断がしやすくなる
2-1. 高精度なパーソナライズ体験…肌・髪・環境などに合わせた提案が当たり前に
2-2. 選びやすさと発見の楽しさ…自宅でバーチャル体験や簡易診断で、選ぶ前の不安を小さく
2-3. 安全性と透明性の向上…成分・由来・製造の透明性が増し、納得して選べる
2-4. ブランドへの親近感と忠誠心の強化…使った後の変化が可視化され、次の選択がスムーズに
3-1. データ偏りによるバイアスや誤判断…一部の肌色や年代、環境だけで学習すると、合わない提案が増える
3-2. プライバシー・データ流用リスク…顔・肌・生活の情報はとてもセンシティブ。取得・保管・共有の設計が肝心
3-3. 規制・表現の不整合の可能性…AIが正しいと過信せず、最終判断は人が行うこと
3-4. AIワッシング(AIの過大宣伝)…魔法のように語る表現は、誤解や過度な期待を招く
3-5. 雇用の変化と人員へのインパクト…ルーチンが整理される一方で、人の役割と学び直しが必要に
AI活用が進むことで、化粧品研究開発は次のステージへ移行します。
肌トーン・性別・年齢層など多様なデータをAIモデルに学ばせ、公平で正確な処方提案や評価を目指す。「暗い肌で精度が落ちる」ような偏りを避けることが、まず最初の処方です。
顔・肌・DNAなど高度にセンシティブな情報を扱う以上、本人同意、匿名化、データ管理体制、情報開示などを厳格にする必要があります。
AIの出力を通じて「美の自信を後押しする」ような設計――ネガティブな自己評価を招かない表現やUI構造を導入し、心理的負担を最小限にするアプローチが求められます。
“AIワッシング”を避け、どこでAIを用い、どこは人が判断したのか、という透明性を消費者に示す。AI利用範囲を明示し、信頼を積み重ねることが重要です。
自動化によって生じる職務変化に備え、従業員がAIを使いこなす研修や、新たな創造的価値創出に関わるキャリア設計を支援する体制を整備しましょう。
AIは、化粧品開発者には「効率・創造・精度の向上」をもたらし、消費者には「自分に合った製品・透明性・新しい体験」を届ける「共創のパートナー」です。効率・透明性・持続可能性を同時に追求することで、化粧品産業は一歩先の未来へ踏み出しています。ただし、偏見・心理リスク・プライバシー・誤認などの課題も併存します。
だからこそ、この技術は「正しく使えば幸せを積み重ねられる処方箋」です。
多様性を守る、安心の仕組みを構築する、人間らしさを尊重する――そんな理念をもとにAIと向き合えば、未来の美しさは、誰もが少しずつ幸せになれるかたちで届くはずです。
参考文献・引用元:
ご希望があれば、そこに御社独自の現場や製品を組み込んで、より具体的な処方箋に仕立てることも可能です。
お気軽にご相談ください。