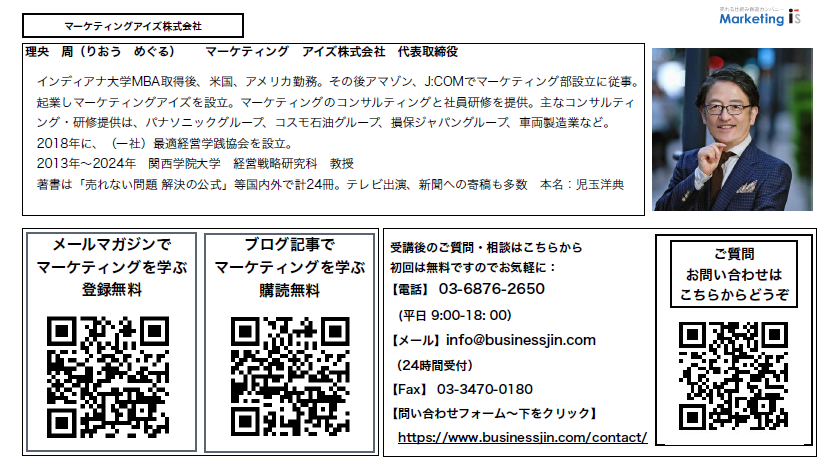ecoだけ ブース
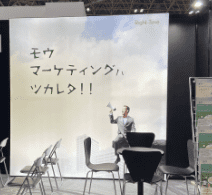
こんにちは。
「エコロジーとエコノミーをビジネス化する」を目標に活動している”ecoだけマーケター“たちが、最近気になる環境やDXにまつわる話題を短く紹介するエコなブログです。「○○したいけど、○○できない」とお悩みの、何かとお疲れ様の皆様に向けて、小さな取り組みなどを紹介します。コーヒーブレイクや休憩の合間にお読みください。

今必要なマーケティングとは?
ビジネスにおいてAIの存在が日常化した今、多くの企業が「AIをどう使うか」という視点でテクノロジー導入を進めています。しかし、本当に問うべきはそこではありません。必要なのは、AIや情報の波に振り回されることなく、自らの頭で考え、使いこなし、成果につなげられる人材と組織をどう育てるかということです。企業が今本当に取り組むべきテーマは、AIを導入することではなく、AI時代に通用するマーケターをどう育てるかにあるのです。
あり方とやり方
AIの進化と共に、今のマーケティングに求められるのは、技術を駆使するスキルだけでなく、顧客の本音や“わがまま”に気づき、それを価値に変えていく感性です。顧客の要望は常に変化し、満足のハードルはどんどん高まっています。だからこそ、顧客の期待を超えた「カスタマーデライト」を生み出す力が、企業の競争力となります。マーケティングの本質は、あくまで顧客価値の創造とその最大化です。売れる仕組みをつくるためには、顧客を理解し、期待を上回る提案をし続ける姿勢、すなわち「あり方」が問われます。そして、その「あり方」を支えるのが、データを読み解き、ツールを使いこなす「やり方」に他なりません。
顧客にとって本当に価値のあるものとは何かを見極める力が不可欠です。自社が誇る製品やサービスに込めた“違い”ではなく、“その違いが顧客にとってどんな意味を持つのか”を伝えられなければ、真の価値にはなりません。自社だけが提供できるユニークな価値、つまりバリュープロポジションを明確に打ち出すことが必要です。顧客が本当に欲しいのは機能の違いではなく、生活やビジネスの中で得られる「意味ある価値」だからです。この本質を理解しないままにAIを導入しても、結果的に安売り競争に陥るだけです。
では、AIは私たちのマーケティングに何をもたらしたのでしょうか。最も大きな変化は、コンテンツの制作スピードと量、そして顧客とのコミュニケーションの質が格段に向上したことです。さらに、従来は手が届かなかった領域にもビジネスを拡張できるようになりました。しかし、その一方で変わらないものもあります。顧客からの信頼を獲得する姿勢や、顧客視点に立った戦略の立案、そして売れる仕組みをつくる努力です。
現在は、マーケティングは人間の価値を再定義しようとしています。大量の情報とコンテンツが日々生み出される中で、本当に必要とされるのは、「誰のために、どんな体験を、どのように届けるのか」という問いを立てる力です。マーケティングが担うべき役割は、体験のカスタマイズによって継続的な関係を築き、安全・利便性・エンタメ性といった“新しい体験”を通じて顧客の心を掴むことにあります。AIの活用目的は単なる自動化ではなく、生産性を高め、顧客体験を向上させ、データドリブンな意思決定を支援することにあります。
たとえば、AIを活用したパーソナライズでは、顧客の購買履歴や嗜好データをもとに個別最適化された提案が可能になります。これにより、満足度やエンゲージメントが高まり、やがて強いロイヤルティを築くことにつながります。需要予測では、天候データやホテルの宿泊人数、過去の売上データを組み合わせて、来店者数や注文内容を正確に予測し、仕入れや在庫管理の精度を上げることで廃棄ロスの削減も実現できます。チャットボットをはじめとする自動応答システムの導入により、顧客対応の質とスピードが向上し、スタッフの負担も軽減されます。
今や、ストーリーテリングやパーソナライズ、顧客との共創は、売れる仕組みの中核となっています。特にBtoBにおいては、商品スペックや価格だけでは顧客の心を動かせません。求められるのは、実体験に基づいたコンテンツ、信頼性のあるデータ、そして共感を誘う語りです。事例紹介やホワイトペーパー、動画やウェビナーといった手段を通じて、顧客の「信頼」「理解」「満足」を段階的に高めていくコンテンツ戦略が重要です。
一方で、AI時代においても変わらないのが“人間の役割”です。発想や顧客理解といった創造的な領域は、AIには代替できません。情報の収集や分析、可視化はAIに任せても、問いを立て、意味を見出し、文脈をつなぎ、ストーリーをつくるのは人間の仕事です。だからこそ、AIを単なるツールとしてではなく、共創パートナーとして位置づける視点が求められます。
AI時代のマーケターの育て方
今後、マーケターに求められるのは、感情を理解し共感を生み出す“顧客力”、創造的に問いを立てて新しい価値を生み出す“創造力”、社内外の関係者を巻き込み推進する“コミュニケーション力”です。これらの力を育てるには、知識と経験を交互に積み重ねる育成アプローチが不可欠です。単なるOJTだけでは属人的になり、Off-JTだけでは実務に応用が利きません。両者を適切にミックスし、抽象と具体の往復で“考える力”を育てる必要があります。
とりわけ重要なのが、「良い問いを立てる力」です。生成AIは、与えられた問い(プロンプト)の質に応じて答えの質が決まります。なぜそれを知りたいのか、誰に向けて何をしたいのか、どんな背景や状況があるのか。こうした前提を深く掘り下げることが、AIを使う価値を最大化するカギになります。
マーケターを社内で育成するには、まずは本質的なマーケティング理解を浸透させ、顧客視点を徹底し、創造と対話の力を実践の中で鍛える必要があります。そのためには、“やらされ感”を払拭し、自ら学び、動く組織文化を育てることが前提です。
育成が単発で終わらないためにも、定期的なフィードバックと目標設定、行動の可視化と共有の仕組みが求められます。自発的に学び、挑戦する風土を醸成するには、社員同士の対話や失敗を許容する文化、共通の目標に向かって協働する「成功循環モデル」を導入するのが効果的です。
特に現場のキーパーソンとなる社員を選抜する際は、顧客理解力、発想力、データ分析、好奇心、調整力など、定性的な観点から選び、段階的な育成プランを用意することが重要です。
属人的な営業活動が限界を迎えつつある今、営業の成果を“仕組み化”していく動きも始まっています。精神論やモチベーション頼りの育成から脱却し、行動と成果を結びつけるプロセスを設計し直すことが求められます。営業会議での共有、現場での実践、フィードバックの循環を通じて、数字を起点とした「気づきと学びの文化」が浸透していくと、組織の底力は確実に上がっていきます。
結局のところ、マーケティングや営業で成果を出すのは「手法」ではなく「行動」です。顧客の心を動かすには、まず企業の内側から、行動を変え、文化を変えていく必要があります。AIを使う時代だからこそ、人にしかできない価値が際立つ。そんな今こそ、マーケター育成の本質に立ち返るタイミングではないでしょうか。