ecoだけ ブース
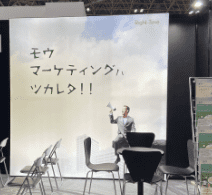
こんにちは。
「エコロジーとエコノミーをビジネス化する」を目標に活動している”ecoだけマーケター“たちが、最近気になる環境やDXにまつわる話題を短く紹介するエコなブログです。「○○したいけど、○○できない」とお悩みの、何かとお疲れ様の皆様に向けて、小さな取り組みなどを紹介します。コーヒーブレイクや休憩の合間にお読みください。

(IMAフォーラム振り返り記事3:第三部【AIを活用したマーケティングの実践】 より要約解説
最新のAIマーケティングで効率を変える
業務のスピードを上げたい、人手不足を補いたい、マーケティング施策をもっと効率的に回したい──
そんな思いを抱えながらも、現場では「やることが多すぎて、考える時間がない」という声がよく聞かれます。
そんな中で、急速に進化している生成AIやAIエージェントの登場により、私たちの“働き方”そのものが変わろうとしています。
すでにAIは、デザインや広告の自動生成、顧客対応、マーケティングオートメーションなど、さまざまな分野で実用化が進み、人手不足を補う単なるツールではなく、“考え、自動で動くアシスタント”としての役割を担い始めています。
本コラムでは、IMAフォーラムで紹介された最新事例をもとに、AIをどう業務に取り入れれば効果を最大化できるのか、どこに導入すべきか、そして“人とAIが共に働く時代”に必要な視点とは何かを、わかりやすく解説していきます。
その前に、INDEXを小説風に紹介しますので、お楽しみください。
【小説】『オレの上司がAIになりまして。』── でも、定時で帰れるようになった件。
「なあ、AIってさ。俺たちの仕事、奪うと思う?」
昼休みの屋上で、同僚の中村が聞いてきた。弁当の玉子焼きを片手に、真剣な顔だ。
「どうだろうな。でも最近、むしろ“助かってる”感あるけどな」
俺はスマホを見ながらそう答えた。そこには、昨日AIが作ってくれた広告文案が表示されている。驚くことに、こっちが指示した通りのトーンで、クライアントが喜びそうなコピーをきっちりまとめてきていた。
思えば数ヶ月前。俺たちの部署に“AIエージェント”が配属された。とは言っても、名札もなければデスクもない。ただ、PCの中に住んでいて、いつも冷静に、でも的確に仕事を片付けてくれるヤツだ。
たとえば調査。ターゲット層の行動パターンとか、過去のクリックデータなんかを一瞬で分析してくれる。マーケティングのペルソナ設計? もうAIが自動でやってくれるから、人間は「ふむふむ」と頷くだけでいい。
文章も画像も、ひとこと命令すれば、プロ顔負けのクオリティで返してくる。パッケージデザインだって、「もっと春っぽく」とか「女性にウケる感じで」と言えば、それっぽいものを何案も出してくるんだ。まるで、超優秀な新入社員が10人分いるみたいな感じだ。
そして極めつけは“追客”。IPMという仕組みを使って、興味を持ってくれたお客さんを、自動で、しかも“今その人が買いたいタイミング”で追いかけてくれる。
こんなやり手が、自分のアシスタントになってくれるんだから、ありがたい話だ。昼休みにのんびりできるのも、最近はこのAIのおかげってわけ。
「でもさ、使いこなせてるのって、うちの部署だけじゃない?」
中村が言う。確かに。AIは魔法じゃない。どこに使うか、何のために使うか。それを人間が見極めないと、ただの“宝の持ち腐れ”になる。
俺たちがやってるのは、AIに任せて終わり、じゃない。AIを使って、自分たちの“判断力”や“発想”を解放してるんだ。
「オレの上司がAIになりまして。」
最初はそう思った。でも今は違う。
AIは“考えてくれる部下”であり、“時間をくれる相棒”だ。
だから、俺たちはもう一度「人間らしい仕事」に集中できる。時代はもう、「AI vs. 人間」じゃない。
「AI × 人間」なんだと思う。
できの善し悪しはさておき、こんなことまで「秒」でできしまう生成AI。実際の業務でも使わない手はないですね。よく知られている文章や画像を生成する以外で、どんな使い方があるのか、さっそく見ていきましょう。
AIを活用した業務改善
調査・広告(オーディエンス広告・ペルソナマーケティング)
現代のマーケティングにおいて、調査と広告はAI活用の第一歩です。AIは膨大な顧客データから行動傾向、興味・関心、属性などを分析し、より精度の高いオーディエンスセグメントを抽出します。従来はマーケターが感覚的に行っていた“誰に届けるか”という設計が、AIによって定量的に判断可能になりました。
また、ペルソナマーケティングにおいても、AIはユーザーのデータを統合的に分析し、多様なペルソナ像を瞬時に生成。例えば、過去の購買履歴やサイトの滞在時間、クリック履歴などから、購買意欲の高いユーザー像を可視化し、それに適した広告メッセージやチャネルを自動で設計することが可能です。これにより、広告の費用対効果(ROAS)は飛躍的に向上します。
コンテンツ(文章作成・画像生成)
生成AIの登場により、文章や画像といったクリエイティブコンテンツの制作が大幅に効率化されています。文章作成では、AIが製品説明やブログ記事、SNS投稿用の短文コピーなどを自動生成し、言葉選びのトーンや表現方法も調整できます。これにより、ブランドトーンを維持しつつ、多量のコンテンツを迅速に発信できるようになりました。
一方、画像生成では、プロンプト(指示文)に応じて、目的に合ったビジュアルをAIが作成します。例えば、パッケージデザインや広告バナー、SNS向けのイラスト素材など、これまでデザイナーに外注していた領域が、社内で迅速に処理できるようになっています。これは、人的リソースの削減だけでなく、制作スピードと表現の多様性という観点でも画期的です。
追客(マーケティングオートメーション・IPM)
追客とは、見込み顧客に継続的にアプローチし、購買や問い合わせへとつなげる施策です。この分野でもAIは極めて有効に機能します。MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用すれば、顧客の行動データをトリガーにして、タイミングと内容を最適化したメッセージを自動配信できます。
株式会社インターロジック 「マーケティングを簡単にしたい」
複雑化するマーケティングにおいて「PALS理論」の実践で成果を創み出す https://interlogic.jp/solution/solution01/
さらに進化した手法として注目されるのが「IPM(インテリジェント・パルス・マーケティング)」です。これはDMやメールで、ユーザーごとのアクセス行動をリアルタイムにトラッキング。興味が高まった“その瞬間”にパーソナライズされたアプローチを行うことで、商談化率を飛躍的に高めることができます。
画像生成について
AIによる画像生成は、デザイン業務の在り方に革命をもたらしています。従来は写真素材やイラストを探し、必要に応じて撮影や描画を行っていた工程が、プロンプト(テキスト指示)を入力するだけで完結するようになりました。AIは膨大な画像データを学習しており、スタイル、構図、配色といった視覚的ルールを理解した上で、ユーザーの意図に即した画像を瞬時に生成します。
CanvaやAdobe Fireflyといった生成AI搭載ツールは、業務における試作・検証のスピードを飛躍的に高め、デザイナーの負担を軽減しています。特にバナーやSNS投稿画像など、量産が求められる分野においては、その効果が顕著です。
デザインレイアウトの自動化
画像生成の次に進んでいるのが、デザインレイアウトの自動化です。これは、テキストや画像をどう配置するかをAIが判断し、視覚的に整ったデザインを自動で構成する技術です。従来はプロのデザイナーの経験とセンスに依存していた領域ですが、AIはA/Bテストや過去の成果データをもとに、どのレイアウトが最もユーザーに届きやすいかを算出できます。
ランディングページやチラシ、パッケージの構成案などが短時間で複数案作成可能になり、顧客との意思決定もスムーズになります。
意思決定プロセスの短縮化
AIデザインがもたらす最大の利点のひとつは、“意思決定のスピード”です。従来は、企画立案→ラフ作成→確認→修正→再確認……という複数ステップが必要でしたが、AIが初期案を即時生成することで、そのサイクルが大幅に短縮されます。
特にクライアントや上層部との意思疎通において、視覚化された案を瞬時に提示できることは、プロジェクト推進の大きな武器になります。意思決定の速さは競争優位に直結し、変化の激しい市場において重要な差別化要素となります。
テキストからのデザイン生成
AIを活用したパッケージデザインでは、プロンプトベースの画像生成技術が新たな可能性を切り開いています。たとえば「女性向け・ナチュラル・高級感」といったテキストだけで、AIはそれに合致するデザイン案を数秒で生成します。こうした生成結果は、従来のブリーフィング→手描きラフ→デジタル作成という長い工程を短縮し、複数案を素早く比較検討するための“たたき台”として非常に有効です。
特に初期段階における方向性確認や、クライアントとのコミュニケーションツールとして、AIデザインの利便性はますます高まっています。
画像とテキストからのデザイン生成
より実用的な応用として、既存の参考画像+プロンプト(テキスト)を組み合わせた生成手法も注目されています。「この雰囲気を維持したまま色を変えたい」「構図はこのままで高級感を加えたい」などの具体的な要望をAIに反映させることができます。
また、ブランディングにおいて重要なCIやVI(ロゴやカラーガイドなど)をAIに学習させることで、ブランド一貫性を保ったデザイン生成も可能です。これにより、デザイナーはゼロから考えるのではなく、“AIと共創する”形でクリエイティブ業務に集中できます。
画像の一部デザインを変更
さらに高度な技術として、画像の一部分のみをAIで変更・補完する「部分修正」機能もあります。例えば、「背景はそのままで商品だけ季節感を加える」「ロゴ位置だけを変更したい」といった細かい修正にも、AIは精度高く対応可能です。
従来であればPhotoshop等で時間をかけて加工する必要があったこうした作業も、AIの補助により、短時間で複数パターンの試作が可能になり、社内プレゼンやABテストにもスピーディに対応できるようになりました。
Metaの広告制作の全工程を自動化する構想
オンライン広告の世界では、広告制作から配信、分析までをAIで自動化する動きが加速しています。特にMeta(旧Facebook)は、広告主が提示した素材や目的に応じて、テキスト・画像・フォーマットの組み合わせをAIが自動で最適化し、パフォーマンスが高いクリエイティブを自律的に選択・配信する構想を進めています。
従来必要だった「ターゲティング設計」「バナー制作」「ABテスト」「レポート分析」などが1つの統合プラットフォーム上で完結。マーケターは細かな作業に追われることなく、戦略設計や成果確認に集中できるようになります。
さらに今後は、ユーザーごとにパーソナライズされた広告がAIによってリアルタイム生成・表示される仕組みも実現が見込まれており、まさに広告は“人の手を離れる”時代に入ろうとしています。
業務効率改善
AIエージェントとは、あらかじめ設定された目標に向かって、自律的にデータを取得・分析し、タスクを実行するAIプログラムです。業務効率化の観点では、こうしたAIエージェントがルーティン業務を代行することで、人的リソースの再配置や処理スピードの向上が期待されます。
たとえば、営業日報の集約やカスタマー情報の自動収集、メール返信の下書き生成など、ホワイトカラーの現場で発生する細かな作業をAIが担うことで、人はより創造性や判断力が求められる業務に集中できるようになります。
自動接客
接客業務においてもAIエージェントの活用は急速に広がっています。チャットボットをはじめとする接客AIは、顧客の質問にリアルタイムで対応するだけでなく、過去の購買履歴や行動ログに基づいた提案・レコメンドを自動で行うことが可能です。
特に、ECサイトでは「24時間対応」「即応性」「パーソナライズ」の3要素が重要視されており、AIエージェントの導入は顧客満足度の向上と同時に、問い合わせ対応の負担軽減にも直結します。今後は音声対応や多言語サポートも進み、“接客の質”も人に近づいていくと予想されます。
クリエイティブ
クリエイティブ領域でもAIエージェントは強力なパートナーとなり得ます。従来、人がアイデアを出し、形にする必要があった広告コピーや商品説明文、画像・動画制作といった作業が、AIの手によってスピーディに生成されるようになりました。
クリエイターはゼロからすべてを考えるのではなく、AIが出力した案を編集・監修するという形で、より効率的にアウトプットを生み出すことが可能になります。特にSNS投稿やキャンペーン制作など、スピード感と量が求められる業務において、AIエージェントは不可欠な存在となりつつあります。
AIをビジネスに導入する際に最も重要なのは、“どの領域に、どの目的で使うのか”を明確にすることです。AIの進化によってあらゆる業務に活用可能な時代になりましたが、すべてを自動化すればよいわけではありません。成功している企業の共通点は、「AIに任せるべき業務」と「人が担うべき業務」を明確に分け、戦略的に活用している点です。
たとえば、ルーティン業務やデータ分析、初期対応などはAIとの親和性が高く、大きな効率化が見込めます。一方で、感情を伴う交渉や、創造的なアイデアの構築といった領域では、AIはあくまで支援ツールとして活用することが望まれます。
AIは“魔法の箱”ではなく、ツールであることを忘れてはなりません。大切なのは、企業ごとの課題やゴールに対して、最も効果的な使いどころを見極める視点です。
AIの本質的な価値は、人間の仕事を奪うのではなく、補完し、拡張するところにあります。私たちはAIを“対等なパートナー”ではなく、“優秀なアシスタント”として活用することで、より多くの可能性を引き出すことができます。
たとえば、タスク管理や日程調整、リマインドといったパーソナルアシスタント的な機能から、ドキュメント作成のたたき台、プレゼン資料の骨子作成、市場調査の要約まで、AIは多くの“準備作業”を効率化してくれます。その結果、人間はより戦略的で創造的な業務に集中でき、成果の質も高まります。
AIは常に指示を待つ存在ではありますが、適切に使えば、まるで“考えて動く部下”のように働いてくれます。業務の中でAIをアシスタントとして自然に取り入れる習慣が、これからの時代における“働き方の標準”になっていくでしょう。