ecoだけ ブース
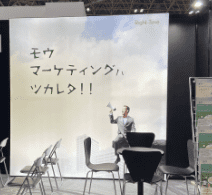
こんにちは。
「エコロジーとエコノミーをビジネス化する」を目標に活動している”ecoだけマーケター“たちが、最近気になる環境やDXにまつわる話題を短く紹介するエコなブログです。「○○したいけど、○○できない」とお悩みの、何かとお疲れ様の皆様に向けて、小さな取り組みなどを紹介します。コーヒーブレイクや休憩の合間にお読みください。

かつて人類は、海の深さと広さに「すべてを受け止めてくれる懐の大きさ」を感じていました。
しかし今、科学者たちはその“最深部”から驚くべき証拠を発見しています。
それは、大量のマイクロプラスチックが深海底の堆積物から検出されたという事実です。
深海は、私たちの目や日常生活にも届かない、静寂に包まれた世界です。
しかし、見えない場所で起きていることこそ、最も深刻な危機なのではないでしょうか。
■ 地球の“最終沈殿地”に集まり続けるプラスチック
プラスチックの海洋流出は、もはや表層の問題ではありません。
使い捨てされたプラスチックは、紫外線や波の力で徐々に細かく砕かれ、5mm未満のマイクロプラスチックとして海中を漂います。軽いものは漂流を続け、重いものや生物の排泄物と結びついたものは、海の底へと沈降していきます。
そして近年の調査では、南極沖、西太平洋海盆、インド洋盆地、そして日本近海など、ほぼすべての主要海域のの深海堆積物から、数千~数万個レベルのマイクロプラスチック粒子が堆積物中に含まれていることが判明しました。これらは「見えないごみ」の象徴であり、沈黙のうちに環境負荷を蓄積し続けているのです。
▽ 国際的な動向
■ 国連環境計画(UNEP)は地球規模での環境問題に対処するための国連の中心的な機関です。1972年の「国連人間環境会議(ストックホルム会議)」を契機に設立され、環境保護を国際政治の主要議題に引き上げた最初の本格的な国連機関です。UNEPの使命は、持続可能な開発を促進し、環境保全をグローバルに調整・支援することで、
・環境に関する国際的な調査・情報提供
・環境問題への政策的助言・支援
・国際条約や枠組みの立案・推進
・持続可能な社会のための技術的・財政的支援
などを主な目的としており、日本も拠出金提供や技術協力を通じ環境技術普及を支援しています。
そして2022年には、「海洋プラスチック汚染を始めとするプラスチック汚染対策に関する法的拘束力のある国際文書(国際プラスチック条約)」の交渉を開始しました。2025年までに合意を目指しており、包括的な流出防止策が期待されています。
■ EUではすでに、使い捨てプラスチック製品の段階的な禁止(EU 指令 2019/904、使い捨てプラスチック指令)と、包装材のリサイクル率向上(包装・包装廃棄物法令(PPWR))が義務化されています。
EUは、海洋汚染や廃棄物問題の深刻化を受けて、2018年以降「循環型経済(Circular Economy)」への移行を加速しています。
・毎年EUだけで2500万トン以上のプラスチックごみが発生
・そのうちリサイクルされるのは約30%以下
・海岸や水域に多く見られるのは使い捨てプラスチック(SUP:Single-Use Plastics)
この現状を踏まえ、EUは「プラスチック戦略(European Strategy for Plastics in a Circular Economy)」を発表し、具体的な法規制に踏み込みました。 主な禁止対象は(2021年より販売禁止)リサイクル困難かつ、他素材で代替可能とされたことが理由です。
・プラスチック製ストロー
・マドラー
・カトラリー(フォーク・スプーン・ナイフ)
・皿(プレート)
・綿棒
・発泡スチロール製食品容器・飲料カップ
・風船の棒 など
EUの環境規制は、規則(regulation)、指令(directive)、決定(decision)、勧告(recommendation)、見解(opinion)の5種類があります。これらの規制は、EU市場に製品を導入する企業にとって遵守が義務付けられています。
主なEUの環境規制の種類:
・ELV指令(廃自動車指令):
廃自動車の再利用やリサイクルを促進し、環境への負荷を軽減する。
・RoHS指令(特定有害物質使用制限指令):
特定の有害物質(鉛、水銀、カドミウムなど)の電気電子機器への含有を制限する。
・WEEE指令(電気電子廃棄物指令):
電気電子機器の廃棄物処理を規制し、リサイクルを促す。
・EuP指令(エコデザイン指令):
製品のエコデザインを推進し、環境負荷の低い製品の開発を促進する。
・REACH規制:
化学物質の登録、評価、認可、制限を定める。
・CLP規則:
化学物質の分類・表示を規制し、人や環境への危害を防ぐ.
・包装廃棄物指令:
包装廃棄物の削減とリサイクルの促進を目指す。
・その他:
ビスフェノール類規制(BPA溶出量に基準)、添加剤規制、CO2排出規制など。
規制内容について
・有害物質規制:
ELV指令、RoHS指令など、特定の有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロムなど)の含有を制限する規制が多数あります
・廃棄物規制:
WEEE指令、包装廃棄物指令など、廃棄物の排出量を減らし、リサイクルを促進する規制があります
・CO2排出規制:
製品のCO2排出量を削減する目的で、エコデザイン規制や排出量取引制度などが設けられています
・化学物質規制:
REACH規制、CLP規則など、化学物質の安全性や環境への影響に関する規制があります
これらの規制は、EU市場への製品の導入を検討している企業にとって、非常に重要な要素です。規制の遵守を怠ると、EU市場への進出が不可能になったり、罰金やその他のペナルティが科せられる可能性があります。
■包装材に関するリサイクル義務化
EUでは、2022年以降、包装材に関する規制も強化されました。
▽ 「包装および包装廃棄物に関する規則案(PPWR)」 ※2022年発表、2024年採択見込み
主なポイント:
1.2030年までにすべての包装材を「再利用可能またはリサイクル可能」に
2.2025年:プラスチック包装材のリサイクル率 50%以上
3.2030年:すべての包装材についてリサイクル設計の義務化
4.再利用可能な包装(リユース容器)導入義務(例:飲食店、EC配送業者)
5.過剰包装禁止や容積・重量比の制限など、過剰包装への対策も
この規制は、EU域内で販売されるすべての製品包装が対象となり、プラスチック以外の素材(紙・ガラス・金属など)にも適用されます。
■ 企業・産業界への影響と対応
・代替素材への転換が急務(生分解性、紙製、再生樹脂など)
・包装設計段階から“リサイクル可能性”を考慮
・サプライチェーン全体での製品ラベル・素材構成の透明化
・リユースサービスや詰め替え容器の導入がビジネスモデルとして拡大
特に食品業界、EC・物流業界、日用品メーカーには大きな影響が出ており、EUに輸出する企業もこの基準を無視できません。
■ 今後の展望
・“リデザイン”の時代へ:包装は単なる保護材ではなく、「再利用・再資源化」を前提に設計される時代に
・デジタル製品パスポート:どんな素材でできていて、どう分別・回収すべきかを消費者にも共有が必須に
・グローバル化:EU基準が世界標準として輸出国にも波及し、日本企業にも影響します
■ 日本企業にとっての意味
・EUの動きは、“規制”であると同時に、“ビジネスチャンス”でもあります
・サステナブル素材の開発や設計力が求められます
・グローバル調達や輸出ビジネスにはEU基準が避けて通れない
・ESG投資や脱炭素の文脈で、プラスチック戦略は企業評価に直結します
深海探査においては、欧州宇宙機関(ESA)やNASAが人工衛星や無人探査機を用いて、マイクロプラスチックの拡散経路を可視化する研究を進めています。
▽ 日本国内の動き
■ JAMSTEC(国立研究開発法人 海洋研究開発機構):海洋や地球に関する科学的研究・観測・技術開発を担う日本の国立研究開発法人です。
深海・海洋・気候変動・地震・地球内部構造など、地球規模の自然現象を総合的に解明し、防災・資源・環境問題に貢献する役割を果たしています。
による深海堆積物の採取と分析では、河川や都市部から海への流入ルートの特定、粒子の組成分析が進んでいます。
■ 主なミッション・目的
JAMSTECの活動目的は、次の4つの柱で成り立っています。
・海洋地球科学の基礎・応用研究
・防災・減災に貢献する研究と情報提供(地震・津波・気象など)
・地球温暖化・気候変動に関する研究と未来予測
・海洋資源や環境保全のための技術開発
■ 国際的な役割と影響力
JAMSTECは、単なる国内研究機関ではなく、国際的にもトップクラスの海洋研究拠点として知られています。
・IODP(統合国際深海掘削計画)など、国際共同研究にも積極参加
・海底火山・地震帯・気候モデルなどの研究成果が国連IPCC報告書やUNEP会議資料にも活用
・欧米の海洋機関(米NOAA、仏IFREMERなど)とのデータ連携・研究協力
■ 海洋プラスチック問題における取り組み
近年では、JAMSTECはマイクロプラスチックに関する深海調査・分析でも注目を集めています。
・深海堆積物からのプラスチック微粒子検出(南海トラフ・伊豆小笠原海溝など)
・流入経路の解明:河川、都市排水、漁業活動、海流との関係を分析
・ポリマー分析・経年劣化モデルの開発による、拡散予測と抑制対策の研究支援
JAMSTECは、深海から気候変動、地震、環境問題まで、地球そのものを丸ごと“研究対象”にする日本の知の拠点です。地球規模での環境保全・災害予測・資源開発といった課題に対して、科学と技術の力で答えを出し続けています。
■ 環境省の海洋プラスチックごみ対策アクションプラン(2020年策定)では、3R(Reduce, Reuse, Recycle)+Renewableを軸とした素材転換や、企業との連携を強化。
日本が国内外で深刻化するプラスチック汚染、とくに海洋プラスチック問題に対して包括的に取り組むための国家的な行動指針です。
この計画の中心にあるのが、「3R+Renewable」という考え方です。
■ アクションプランの背景と目的
背景:
・世界の海に毎年流出するプラスチックごみは約1,100万トンと推定され、日本もその一部を担っています
・海洋生物の誤食・生態系の破壊・食物連鎖への影響・観光資源の損失など、多面的な問題が顕在化
・G20大阪サミット(2019)では「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン(2050年までに海洋プラごみゼロ)」が提唱され、日本がその実現の牽引役を担うことに
目的:
・海洋に流出するプラスチックごみを徹底的に抑制
・国内外の官民連携を強化し、循環型社会の国際モデルを目指す
■ 3R+Renewableの基本方針
・Reduce(リデュース)
プラスチック製品の使用そのものを削減(例:使い捨てストローやレジ袋の削減)
・Reuse(リユース)
再使用可能な容器・包装材の推進(例:リユースボトル、詰替え式容器)
・Recycle(リサイクル)
資源として再利用しやすい設計とインフラ整備(素材の単一化、水平リサイクル等)
・Renewable(リニューアブル)
再生可能資源(バイオマス、植物由来樹脂)などへの素材転換
この「3R+Renewable」は、プラスチック製品のライフサイクル全体を見据えた抜本的改革の方向性とされています。
■ 具体的な施策と企業連携の強化
① 素材転換の推進
・バイオマスプラスチック導入補助金制度
・生分解性プラスチックの開発支援
・農業用資材、漁業用ブイ、食品包装などで石油由来素材からの置き換えを加速
② デザイン・製品開発段階での支援
・製品設計ガイドラインの策定(例:リサイクル適正設計ガイドライン)
・容器包装の単一素材化・着色制限によるリサイクル効率向上
③ 企業・自治体との連携プロジェクト
・プラスチック資源循環促進協議会の設立
・小売・外食・メーカー・自治体が連携し、地域循環モデルを構築(例:詰替えパウチ回収、再商品化)
・地域ごとの“見える化マップ”を活用した排出・流出源の特定と重点対策
④ 国際連携
・アジア諸国との技術支援(JICAやADBと連携)
・ASEANプラスチック戦略への協力や技術・資金提供
■ 今後の課題と展望
・コストの壁
バイオマスや生分解素材は価格が高く、普及には補助や需要創出が必要
・市民の参加意識
分別やマイボトル利用など、消費者行動の変化が不可欠
・サプライチェーンの統合
製造~販売~回収~再生の仕組みを業界横断で構築する必要
・国際基準との整合性
EUやUNEPと協調し、グローバルルール対応を進める必要がある
環境省のアクションプランは、「作る側・使う側・捨てる側」すべてが変わることを求める未来志向の政策です。
単なる「ごみ問題」ではなく、製品設計・原材料調達・企業責任・市民参加が連動した“資源循環の再設計”といえます。
「プラスチックとのつきあい方を、根本から変える」。
それが今、私たちに求められている第一歩です。
■一部の地方自治体や企業では、漁網・食品トレー・パッケージを生分解性素材へ移行する実証実験が行われています。
・用途ごとの適材適所での素材選定が鍵(海中使用には分解速度調整型素材など)
・国や自治体によるインセンティブ制度(補助・税制優遇)が普及の後押しに
・包装材や漁具の標準化・統一規格化が、製造側・回収側の効率化につながる
・国際市場でも「バイオ対応商品」への関心が高まっており、輸出品の付加価値化にも期待
漁網・食品トレー・パッケージの生分解性素材への移行は、脱プラスチック時代の試金石といえます。
実証実験の成果を活かしつつ、コスト・耐久性・インフラとの整合をどうとっていくかが今後のカギ。
そして、「海に流れても安心な素材」ではなく、「そもそも流さない設計と仕組み」との組み合わせこそが、本当の解決策です。
深海は、「時間が止まる場所」とも呼ばれます。光も届かず、微生物活動も遅い環境では、分解はほぼ進みません。つまり、一度沈んだマイクロプラスチックは“永続的な負荷”として残り続けるのです。
さらに、深海生物がこれらを誤食し、食物連鎖を通じて水産物に取り込まれるリスクも高まりつつあります。漁業国・海洋大国である日本にとって、これは経済・健康・国際信頼のいずれにおいても看過できない問題です。
■ 私たちが直面する課題とハードル
回収困難性
マイクロサイズのため物理的に分離が困難、下水処理場・家庭排水にフィルター設置が必要
素材の転換遅れ
バイオ素材や生分解性素材は高コスト、税制優遇・大量供給による価格低下が不可欠
国際的な足並みの不一致
発展途上国では処理インフラが未整備、技術移転・ODA型支援・国際枠組みが必要
企業の動機付け不足
バージンプラスチックの方が依然安価、ESG評価・グリーン調達義務などがカギ
■ 実現可能な解決策:今すぐ動ける4つのアクション
マイクロプラスチックの問題は、「人間の目に見えないからこそ、社会全体で対処しなければならない」という新たな環境課題です。
これを放置すれば、いずれそれは「食卓にのぼる問題」へと姿を変え、私たち自身に返ってきます。
深海からの“静かな警告”を、見過ごすわけにはいきません。
次の世代に引き継ぐべきは「便利さ」ではなく、「責任ある選択」なのです。
