ecoだけ ブース
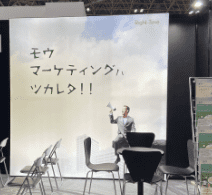

日々、私たちは商品を手に取るたびに、無意識のうちにそのパッケージにも触れています。ですが、皆さんはそのパッケージが「使った後にどうなるのか」を意識したことがあるでしょうか?
使い終わった後のパッケージは、分別してゴミ箱へ。けれど、それは“終わり”ではありません。焼却されてCO2を排出し、分解されずに海に流れ出し、未来の環境に影響を与え続ける「始まり」でもあります。
いま世界では、消費者がサステナブルな選択を基準にし始めています。しかし、選択肢の多さや、どこまで環境に配慮されているのか分かりづらいことで、混乱や“エコ疲れ”を感じる人も少なくありません。
だからこそ、企業が一歩先んじて、「環境に配慮された姿勢」をわかりやすく示す必要があります。その最前線にあるのが、「パッケージデザイン」です。
==========================================
1.パッケージが語る企業の姿勢
2.環境配慮型パッケージが求められる背景
3.見直したい「5つの視点」── 環境負荷低減の実践フレーム
4.未来に選ばれるパッケージとは
==========================================
パッケージは単なる“梱包材”ではありません。それは企業の理念やメッセージを静かに語る「無言のメディア」です。
製品の性能や価格だけでなく、「どんな思想でこの商品がつくられているか」への関心が高まっている今、パッケージは最も身近なコミュニケーション手段でもあります。
サステナブルなパッケージは、
・消費者に企業姿勢を伝える
・ブランドへの共感を生み出す
・ESG投資やSDGs評価にもつながる
といった、大きな価値を秘めています。
現在、世界は「脱炭素社会」「資源循環型社会」への大きな転換期にあります。環境規制の強化や、ESG投資の拡大、企業の環境情報開示の義務化なども進んでいます。
その中で、企業に求められるのは単なる環境配慮の姿勢ではなく、「具体的な取り組み」と「可視化されたアクション」です。パッケージは、その取り組みを具体的かつ視覚的に示す格好の手段といえます。
① Reduce(リデュース)—「減らす」
・材料の使用量を抑える(軽量化・薄肉化)
・過剰包装の見直しで資源の無駄を削減
・紙とプラスチックの複合素材の簡素化で分別しやすく
ポイント: 材料使用量そのものを抑えることで、資源の消費と廃棄物の発生を削減します。軽量化や薄肉化、過剰包装の見直しが主なアプローチです。
注意点: 強度や保護機能のバランスを見誤ると、製品の品質や安全性に影響するため、設計段階での検証が重要です。
② Reuse(リユース)—「繰り返し使う」
・リフィル(詰め替え)容器の採用
・ガラス瓶や金属缶など耐久性のあるパッケージの活用
・リターナブルボトルや回収型物流コンテナの導入
ポイント: 耐久性のある容器や詰め替え対応型の設計によって、パッケージを複数回使用可能にします。環境負荷の低減に加え、消費者のコスト意識にも合致します。
注意点: 回収や再利用の仕組み、衛生管理の体制構築が不可欠です。ユーザーの利便性も意識した設計が求められます。
③ Recycle(リサイクル)—「再資源化する」
・モノマテリアル設計で分別しやすく、再生率を向上
・再生材(PCR材)を使用して新たな資源利用を減らす
・使用済みパッケージの回収・リサイクルの仕組みづくり
ポイント: 使用済みパッケージを原料として再生利用することで、新たな資源採取を抑制します。単一素材(モノマテリアル)設計や再生材(PCR材)の利用が推奨されます。
注意点: 地域ごとのリサイクルインフラに適合した設計が必要であり、分別しにくい複合素材は避けるべきです。
④ Sustainability(サステナビリティ)—「持続可能性を追求する」
・生分解性素材や植物由来のバイオマス素材を使用
・FSC認証紙など、持続可能な資源調達への配慮
・製品ライフサイクル全体(LCA)を見据えた設計
ポイント: 製品ライフサイクル全体(LCA)を視野に入れた、持続可能な素材やエネルギー活用による設計です。バイオマスプラスチックやFSC認証紙などの使用が含まれます。
注意点: サステナブル素材はコスト高の場合もあるため、製品価格への影響とブランドの付加価値をどう結びつけるかが課題となります。
⑤ CO2削減(脱炭素)—「カーボンフットプリントの低減」
・原材料の選定と輸送方法の見直しでCO2排出を抑制
・軽量化による輸送効率の向上
・再生可能エネルギー活用やカーボンオフセットの取り組み
ポイント: 製造・輸送・廃棄の各段階でCO2排出を最小化する設計。原材料選定や軽量化、再生可能エネルギーの導入が中心です。
注意点: CO2排出量の「見える化」や算出方法の明確化がないと、効果が伝わりづらくなります。LCA評価やカーボンオフセットも併用が効果的です。
もはや環境配慮は“選択肢”ではなく、“前提条件”です。とはいえ、ただ環境に優しいだけのパッケージは、もはや差別化要因にはなりません。
これから必要とされるのは、
・機能性
・デザイン性
・持続可能性
を高いレベルで融合させた、“選ばれるパッケージ”です。
その設計思想ひとつで、企業は「時代遅れ」になるか、「未来をつくる存在」になるかが分かれます。
サステナビリティはCSR活動ではなく、企業の競争力そのものです。
パッケージを変えることは、ブランドの信頼を高め、社会課題への対応を進め、ひいてはビジネスを進化させる最も手軽で、かつ効果的な第一歩になります。
未来を見据えた戦略的なパッケージづくり。今こそ、御社の「選ばれる理由」をパッケージで可視化してみませんか?
NAGANAE PACKAGE|長苗印刷株式会社 パッケージ事業部 https://ecodakemarke.naganae.co.jp/packagesample/
■お問い合わせ:長苗印刷株式会社 パッケージ事業部 n-package@naganae.co.jp.